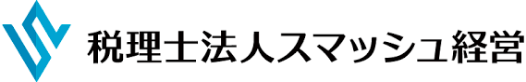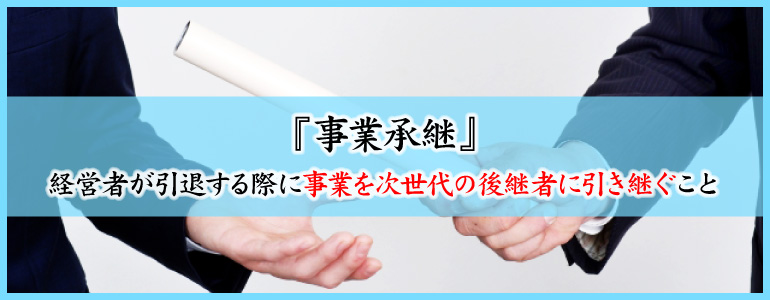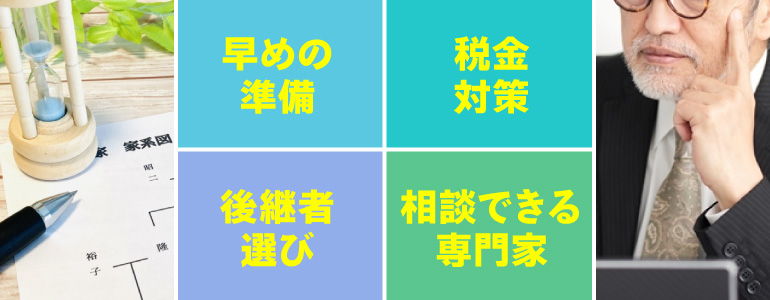相続情報
2024.06.03
事業承継とは?承継先の3つの選択肢と進め方・注意点まで詳しく解説
事業承継とは、経営者が引退する際に事業を次世代の後継者に引き継ぐことです。事業承継では、人的資源、資産、知的資産など、経営権だけでなくさまざまなものを引き継ぎます。
当記事では、事業承継の基本的な概念や承継方法の選択肢、実際に事業承継を進めるステップなどを、詳しく解説します。親族内承継、従業員への承継、第三者への承継(M&A)といった選択肢のメリットとデメリットも詳細に掘り下げますので、事業承継について悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
1.事業承継とは?
事業承継とは、経営者が引退する際に事業を次世代の後継者に引き継ぐことです。事業承継で次世代に引継ぐものには、大きく分けて人・資産・知的資産という3つの要素があります。
| 引き継ぐもの | |
|---|---|
| 人の承継 | 経営権 |
| 資産の承継 | 株式、事業用資産(設備、不動産など)、資金(運転資金、借入など) |
| 知的資産の承継 | 経営理念、知的財産権(特許など)、技術、ノウハウ、人脈、信用、顧客 |
(中小企業庁 2017版小規模企業白書「第2部 小規模事業者のライフサイクル」第2-2-1図参照)
人の承継では、経営者が事業を担う後継者を選び、経営権を譲渡します。多くの場合、後継者選びには時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。また、法人の場合、経営権を引き継ぐ際は、株主総会の決議で選任される必要があります。その後、役員変更登記などの手続きを経て、事業の経営権が移ります。
資産の承継とは、株式や不動産、資金といった物的資産のことです。譲渡や相続、売買によって承継しますが、株式会社の場合、株式を承継すると、自動的に設備や不動産も引き継がれます。資産の承継は、方法によってかかる税金が異なるため、注意が必要です。専門家に相談の上、慎重に進めるとよいでしょう。
技術やノウハウ、人脈などの知的資産は、企業を存続、成長させる上で欠かせない要素です。経営権の譲渡と合わせて、計画的に知的財産を引き継ぐ必要があります。特に、ステークホルダーから、事業承継についての理解を得ておくことは重要です。
なお、事業承継の似た用語として「事業継承」があります。意味に大きな違いはありませんが、「継承」は地位や財産など形あるもの、「承継」は無形で抽象的なものを受け継ぐ意味合いが強いです。事業の引き継ぎに関しては、一般的に「承継」が使われます。
2.事業承継の3つの選択肢
事業承継には、大きくわけて親族内承継・従業員への承継・第三者への承継(M&A)という3つの選択肢があります。それぞれメリット、デメリットがあり、企業によっても最適な方法はさまざまです。
2-1.親族内承継
親族内承継とは、経営者の子や孫、甥、姪、兄弟などの親族に、経営を引き継ぐことです。日本では、中小企業を中心にファミリー企業が多く、親族内承継が一般的な方法として知られています。
親族内承継のメリットは、早い段階から後継者の選定や育成ができる点です。取引先や現場といった社内外での経験を積ませることで、後継者の経営能力を育むケースもあります。親族内承継はポピュラーな方法であるため、従業員や取引先からの納得を得やすいのもメリットです。また、親族の場合、贈与税や相続税において、税制上の優遇措置を活用できます。
一方で、後継者不足や親族間の不和などにより、親族内承継が円滑にいかない場合もあります。親族が承継を拒否する場合や、親族に重い責任を負わせたくないという理由で、経営者が親族内承継を選ばないケースも珍しくありません。近年では、親族内承継をする企業は減少傾向にあります。
2-2.従業員への承継
親族以外の従業員に事業を承継する方法もあります。従業員承継は、経営者とともに長く仕事をしてきた人が選ばれるのが一般的です。そのため、企業の経営理念や人脈、社風などの知的資産を承継しやすいメリットがあります。親族内承継では後継者の候補が限られますが、全従業員の中から後継者を選ぶとなれば、選択肢は大きく広がるでしょう。
ただし、従業員承継では、資産の承継に注意が必要です。法人の場合、後継者は、株式を買い取る際に、資金を用意しなければなりません。対策としては、後継者への給与を増やす、後継者が元経営者に分割で支払う、金融機関やファンドを活用するなどが挙げられます。
また、従業員への承継では、他従業員や親族から後継者について理解を得られるよう、十分な説明が必須です。
2-3.第三者への承継(M&A)
親族内承継、従業員承継が困難な場合であっても、第三者にM&Aをすることで、事業を承継できます。M&Aとは「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略です。M&Aであれば、企業内に後継者がいなくても、従業員の雇用維持が可能です。
第三者承継では、譲受企業の実績やリソースを使って、事業の更なる成長が見込めます。また、法人の場合、株式を譲渡すれば、売却資金が手に入るメリットもあります。
デメリットは、創業時からの社風やビジョンが変わる可能性があることです。第三者への承継は、譲受企業とのマッチングが重要です。企業の調査と選定は慎重に行いましょう。
3.事業承継を進める方法
事業承継をスムーズに進めるためには、早くから後継者を検討し、準備に取り掛かることが大切です。一般的には、以下のようなステップで事業承継を進めます。
| 1 | 後継者を決める |
|---|---|
| 企業内に、親族など、後継者に適した人材がいるかを検討します。後継者の育成には時間がかかるため、早い段階から適任者を探し、承継の意志を確認しておきましょう。会社内に後継者となる人がいない場合は、第三者承継を視野に入れます。 | |
| 2 | 企業の現状を把握する |
| 後継者に引き継ぐ準備として、企業の現状を分析しておきます。具体的には、財務状況や業界の将来性や課題、従業員の状況などです。現状の把握は客観性が求められるため、専門家や金融機関に依頼するとよいでしょう。 | |
| 3 | 経営改善を進める |
| 企業の現状把握で明らかになった問題点は、後継者に引き継ぐ前にできる限り改善を進めます。財務状況の改善はもちろん、新たな人材確保や法令順守体制の確立も重要です。 | |
| 4 | 事業承継計画を決める |
| 事業承継では、企業の10年後を見据えた事業承継計画の策定が必要です。企業の現状と今後の経営計画、事業承継の時期や項目などをまとめます。後継者に引き継ぎたい理念も盛り込むとよいでしょう。取引先や従業員、金融機関との関係性を考慮することも大切です。 | |
| 5 | M&A等のマッチングを行う |
| 第三者へ承継する場合は、M&A等のマッチングを進めます。企業の社風やビジョンを守るためにも、あらかじめ譲渡条件や要望を明確化しておきましょう。 | |
| 6 | 事業承継を実施する |
| 事業承継の実施では、法的手続きや税金対策が重要になります。弁護士や税理士、公認会計士といった専門家にサポートを依頼すると安心です。 | |
4.事業承継を行うときの注意点
事業承継でトラブルが発生してしまうと、企業に大きな損失を与えます。事業承継の準備を怠ったために、廃業を余儀なくされるケースもあります。事業承継を行うときは、以下の点に注意しましょう。
・早めに準備を行う
一般的に、事業承継には5~10年ほどの期間が必要だと言われています。いつまでも働けると過信せず、早い段階から後継者選びを始めましょう。また、後継者が必ずしも事業承継を承諾してくれるとは限りません。後継者育成や手続き、外部からの理解を得る期間も含め、余裕を持って計画することが重要です。
・税金対策を行う
株式や不動産といった資産を承継する際は、納税の必要があります。承継方法によっては特例制度を活用できることもあるため、税理士などの専門家に相談しながら、節税対策を行いましょう。
・後継者を慎重に選ぶ
経営者によって、企業の業績は大きく左右されます。後継者選びは、実務経験やリーダーシップ、人望などを総合的に判断して、慎重に進めましょう。また、他者の意見を柔軟に取り入れる姿勢や、企業を支える覚悟と忍耐力も、後継者選びのポイントです。
・相談できる専門家を作っておく
事業承継では、さまざまな専門知識を必要とします。弁護士や税理士、公認会計士、中小企業診断士といった専門家に、サポートを依頼しましょう。商工会議所や事業引継ぎ支援センター、金融機関、事業承継を専門とするコンサルタント企業などに相談する方法もあります。
まとめ
事業を次世代の後継者に引き継ぐことを事業承継といい、企業の存続と発展のためには計画的に事業承継の準備を進めておく必要があります。後継者を選ぶだけでなく、現状の分析と経営改善の実施、事業承継計画を策定しておくことで、スムーズな事業承継が可能です。
また、税金対策や法的手続きに関しては、専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。事業承継は単なる経営権の移行ではなく、企業の未来を形作る戦略的な決断であることを念頭において、準備を進めましょう。
監修者情報

税理士法人スマッシュ経営
森田 光昭(もりた みつあき)
資格:税理士
経歴
- 1952年
- 名古屋市生まれ
- 1976年
- 名古屋国税局採用
- 1992年
- 名古屋国税不服審判所審査官
- 1995年
- 資産税担当統括官
- 1997年
- 名古屋国税局国税訟務官室主査
- 1999年
- 名古屋国税局資産課税調査部門総括主査
- 2001年
- 特別国税調査官(評価)
- 2003年
- 評価専門官
- 2008年
- 名古屋国税局税務相談室相談官
- 2010年
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得
宅地建物取引士資格取得 - 2011年
- 名古屋国税局税務相談室主任相談官
- 2013年
- 評価専門官付調査官
- 2015年
- 評価専門官付上席調査官
- 2017年
- 資産税審理担当上席調査官
- 2018年
- 名古屋国税局退職
税理士登録
税理士法人スマッシュ経営 名古屋オフィス入社